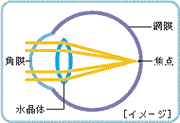「見える」ということ
私たちは一体どのようにしてものを見ているのでしょうか?
私たちはものを見る時、「水晶体」という目のレンズを厚くしたり薄くしたりして、見たい対象にピントを合わせています。近くを見る時は厚くなり、遠くを見る時は薄くなります(もとの厚さに戻ります)。ちょうど、カメラで遠くのものや近くのものを上手に写すためにピントを合わせるのと同じです。このような水晶体の働きを「調節」といいます。
では、どういう時にものがよく見えて、どういう時によく見えない状態になるのでしょうか?
遠くから光が目に入ってきた時、ものを見るために必要な神経が集中している「網膜」という場所で光がきちんと像を結べれば、よく「見える」状態になります。これを「正視」といいます。しかし、この時網膜できちんと像を結ぶことができなければ、よく「見えない」状態になってしまいます。よく「見えない」状態には、「近視」、「遠視」、「乱視」、「老視」の4つがあります。
瞳も呼吸しています
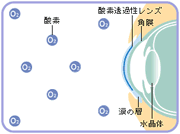
ハードコンタクトレンズのイメージ図
呼吸は口や鼻からだけでしているのではありません。「皮膚呼吸」という言葉がありますね。皮膚は自らも呼吸をしながら新陳代謝を行っています。同様に瞳も新陳代謝をするために呼吸しています。その働きを行う「角膜」は皮膚よりもデリケート。酸素が不足すると、正常に働かなくなってしまいます。だから、レンズが酸素を通す量をあらわす「酸素透過係数(Dk値)」も大切なコンタクトレンズ選びのポイントなのです。